
|
ンの観客が好むすべてのものが入っていたのだろう。
オッフェンバックは眠っていた子を起すようにジングシュピールが大好きだったウィーンっ子に再び、ジングシュピール熱をかきたてた。今度はオペレッタという名で−。
『こうもり』は人間の音楽喜劇
ワルツ王ヨハン・シュトラウスにとってこのオペレッタは、『インディゴと40人の盗賊』(1871)、『ローマのカーニヴァル』(1873)に次ぐ3作目だった。だが『こうもり』には、オペレッタのすべてのみならず、前述したコンメディア・デッラルテも、ジングシュピールも、フォルクステアターの伝統も、みんなごく自然に入っているのである。フランスの第二帝政時代に生きたメイヤックとアレヴィの喜劇『真夜中の晩餐』を原作としてハフナーとジュネーが書いた台本を読み、ワルツ王が、湧き起った感興を自然に素直に、曲げることなく五線譜に、1873年のクリスマスも終る頃から43日間、寝食を忘れ書きしるした−それが『こうもり』である。1874年4月5日、テアター・アン・デア・ウィーンで初演された『こうもり』には、当時の世相が、人情が、斜陽貴族と新興ブルジョアジーといった“生きてる時代の気分”がすっぽり入っていた。
天才としかいいようがない。芸術とは土であり、時代とのめぐり会いだ、と『こうもり』をみるとつくづく分かる。
こんなに時代の気分にぴったりな、その時代の最先端をいった『こうもり』。では時代が過ぎたら流行と同じで、古くなって見向きもされなくなったのだろうか。とんでもない。『こうもり』はウィーンが生んだ永遠に枯れることのない大輪の花なのだ。なぜなら、それは音楽の中に、いつに変ることのない人間の本質が、男女の機微が深く描かれているからである。男と女の愛、「恋はゲーム、愛はプレー」といいながら、その中に切ない真実の愛が得もいわれないワルツの中からこぼれ出るからだ。
ウィンナ・オペレッタの最高峰『こうもり』は、時代を超え、国境を越え、民族を越え、日本人にもよく分る“人間の音楽喜劇”である。
日本ならではの“シャンパン・オペラ”−伝統の融合
台本・演出にあたっては、ウィーンの伝統と日本の伝統をごく自然に融け合わせ、シャンパンのように軽やかで爽快な、日本ならではの“シャンパン・オペラ”『こうもり』を創造した。
『こうもり』はいわばウィーンの『忠臣蔵』。一世紀も上演し続けていると自然と歌舞伎の型のようなものが生まれてくる。その型をしっかり継承した上で、原作の「あ
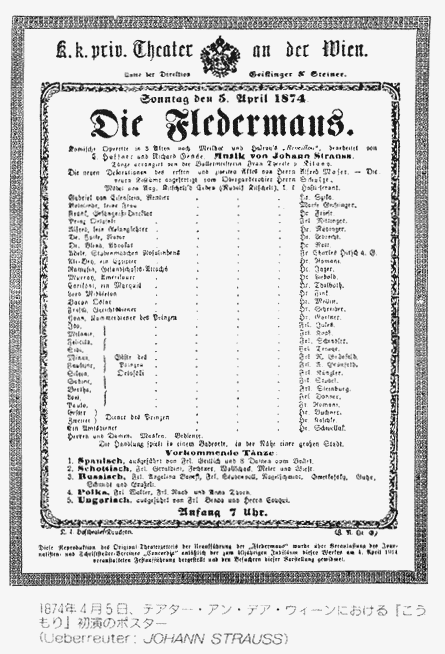
る大都会近郊の湯治場、大晦日の昼下りから元旦の朝まで」を、忠実に再現。オルロフスキー公爵邸の夜会のクライマックスでは、ちょうど新年となり、シャンパンの礼砲とともにシャンパンの歌「ぶどうが燃えたぎって」があふれ出る。そして、大都会すなわちウィーン近郊の湯治場、バーデンの明るくサニーな、“シャンパン・オペラ”にふさわしい舞台を創り上げた。たとえば幕切れ、あの辛気くさい刑務所の壁は飛び、オルロフスキー公爵邸の広々とした天窓に新年の雪が降る。人々は「シャンパンこそ酒の王様」を讃え、公爵の小姓ミーシャは宙乗りで“こうもり”となり、小さなこうもりの傘を手に、囚人服を着たアイゼンシュタインを先導し、フロッシュが舞台中央階段に連行する。一同は大笑い。かくて“シャンパン・オペラ”『こうもり』は、もの皆、歌と笑いで幕、という趣向だ。
『こうもり』は、アイゼンシュタインに“こうもり”と渾名をつけられ、ウィーン中の笑い者にされたファルケが、オルロフスキー公爵邸の夜会を舞台に、自らの作・演出の人間喜劇「“こうもり”の笑いの復讐」を展開するドラマだ。しかし、その“復讐”には憎悪がない。そこには、人間がいつも常識とか義理とか倫理とかで押ししずめている欲望、いうならば“人間願望”のすべてがか
前ページ 目次へ 次ページ
|

|